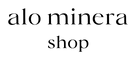大事なミネラル 亜鉛
今日は、ミネラルのひとつである亜鉛についてのお話です。最近では味覚異常と亜鉛の関わりが話題に上がっていたこともあり、注目のミネラルですね。亜鉛は細胞分裂に関わるため、成長には欠かせない物質です。成長期の子ども、病気やケガの治癒時には必要量が増加するということも覚えておきましょう。
亜鉛のはたらき
亜鉛は体内に約 2,000 mg 存在し、主に筋肉、骨、皮膚、肝臓、脳、腎臓などに分布しています。亜鉛と結合することで機能する酵素や転写因子、シグナル伝達物質などは300種類以上ともいわれて、亜鉛は人間の身体機能の維持には必要不可欠です。
そして何より、亜鉛は細胞分裂に欠かせない存在であり、生殖機能に大きく関わります。
男性では特に精巣や前立腺に亜鉛が高濃度に含まれており、性機能との関わりも示されています。
DNAを合成する酵素である、DNAポリメラーゼ、RNAポリメラーゼに亜鉛が必要です。身体のタンパク質はDNAを基につくられるため、亜鉛が不足すればタンパク合成が低下し、異常タンパクが増加すると考えられます。
亜鉛不足による症状
亜鉛不足が引き起こす症状をいくつか挙げてみましょう。
- 味覚異常
味を感じる細胞「味蕾(みらい)」 は細胞分裂が盛んで、亜鉛を必要とします。亜鉛が不足すると「味がわからない」「何を食べても同じ味」といった症状が起こります。よく「病院食が不味い」といわれることがありますが、それは亜鉛不足による症状だとも考えられています。
- 皮膚炎
皮膚細胞も生まれ変わりのスピードが速いため、亜鉛が必要とされます。ターンオーバーといわれるように、どんどんと新しい皮膚が生まれますが、亜鉛が足りないとターンオーバーに影響が出て皮膚炎やアトピー症状につながります。
- 認知力低下
亜鉛は、記憶を司る海馬と呼ばれる場所にも多く存在しているため、記憶力とも関わります。
- 免疫力低下
免疫細胞の機能を向上させる場所である胸腺は、亜鉛が欠乏すると萎縮してしまうことがわかっています。
その他にも、体内での銅と亜鉛のバランスが悪いと不安や恐怖、焦燥感を感じて攻撃性が高まったり、インスリン分泌に影響が及び糖尿病の原因になったりなど、実に多くの問題と関わります。

積極的に亜鉛を摂取しよう
亜鉛が多く含まれる食品として代表的なのは牡蠣ですね。他にはウナギ、レバー、アーモンド、切干大根などが挙げられます。一方で、亜鉛の吸収を阻害してしまうものも存在します。食品添加物に含まれるリン酸塩、精製食品、そしてストレス、さらに胃酸分泌量の不足などが亜鉛吸収を妨げてしまうのです。外食の機会が多かったり、頻繁にコンビニを利用したりする方は亜鉛不足のリスクが高まります。またアルコール代謝時にも亜鉛が必要なため、アルコール摂取量が多い場合には、必要量も増加します。このように食品添加物やアルコールの弊害を考えた上で、日々の食生活を少し意識していきましょう。